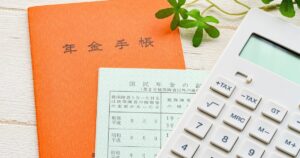「事業が軌道に乗って売上が増えたのは嬉しいけれど、税金と保険料を引くと手取りが全然増えていない……」
「国民健康保険料の通知書を見て愕然とした。年間80万円? これって何かの罰金?」
フリーランスや個人事業主として成功し、年収(所得)が500万円を超えてきたあたりで、誰もがぶつかる巨大な壁。それが**「国民健康保険料(国保)の負担」**です。
会社員時代は会社が半分負担してくれていた社会保険料ですが、独立すると全額自己負担。しかも、国保は「稼げば稼ぐほど青天井(上限までは)」で上がっていく仕組みのため、頑張って稼いだ利益が保険料として消えていく現実に、やるせなさを感じる方も多いのではないでしょうか。
そんな「国保地獄」に悩むフリーランスの間で、今、合法的かつ効果的な「最適解」として注目されている手法があります。
それが、「個人事業」と「小さな会社(マイクロ法人)」を同時に持つ「二刀流」スキームです。
この記事では、所得が上がって国保の負担に限界を感じている方に向けて、**「マイクロ法人を活用して、社会保険料を年間数十万円単位で安くする仕組み」**について解説します。
怪しい裏技ではなく、国の制度を賢く利用した「防衛策」を学び、手元に残るキャッシュを最大化しましょう。
なぜフリーランスは損をする?「国保」の限界と高負担の正体
解決策の話に入る前に、まず「なぜ今のままでは損をし続けるのか」、その構造的な欠陥を整理しておきましょう。
フリーランスが加入する「国民健康保険」は、高所得者にとって非常に厳しい設計になっています。
1. 稼ぐほど上がるのに「補償」は薄い
会社員が加入する「社会保険(健康保険+厚生年金)」と、フリーランスの「国保+国民年金」。
両者を比べたとき、国保は**「ハイコスト・ローリターン」**と言わざるを得ません。
例えば、会社員なら病気で働けなくなったときに給料の約3分の2が補償される「傷病手当金」や、産休中の「出産手当金」がありますが、国保には原則としてこれらの制度がありません。
「保証は薄いのに、保険料だけは高い」のが、ある程度稼いでいるフリーランスの現状です。
2. 扶養家族が増えるほど「罰金」のように増える
これまでの記事でも触れましたが、国保には「扶養」という概念がありません。
会社員であれば、年収1000万円あっても、専業主婦の妻や子供の保険料は「タダ(追加負担なし)」です。
しかし、国保の場合は家族一人ひとりに「均等割」という基本料金が加算されます。
「稼いで家族を養おうとしているのに、家族が増えるほど保険料を取られる」
この仕組みが、子育て世代のフリーランスを苦しめる最大の要因となっています。
解決策は「マイクロ法人」!社会保険料をミニマムにする仕組み
そこで登場するのが**「マイクロ法人」という選択肢です。
これは、事業を大きくするための会社設立(起業)とは少し意味合いが異なります。あくまで「税金と社会保険を最適化するための箱」**として会社を作ります。
そして重要なのは、個人事業を廃業して法人成りするのではなく、**「個人事業主」としての活動も残したままにする(=二刀流)**という点です。
マイクロ法人とは?
従業員を雇わず、社長(あなた)1人だけで運営する小規模な会社のことです。
自宅を本店にし、最低限の事業内容で運営します。
【図解解説】社会保険料を劇的に下げる「二刀流」のカラクリ
仕組みは意外とシンプルです。日本の社会保険制度の「ルール」を逆手に取ります。
- 「個人事業」と「法人」で売上を分ける
- 個人事業(A): 本業の売上(デザイン、執筆、エンジニア業務など、大きく稼ぐ事業)はこちらに残します。青色申告特別控除などのメリットを使い倒します。
- マイクロ法人(B): 手間のかからない、売上の小さな事業(資産運用、ブログ運営、一部のコンサル契約など)を法人で契約します。
- 法人の役員報酬を「最低額」に設定するここが最大の肝です。法人から社長である自分に支払う給料(役員報酬)を、月額4万5000円程度に設定します。
- 社会保険は「法人」で加入する法人の役員になると、強制的に「社会保険(健康保険+厚生年金)」に加入することになります。すると、個人で加入していた「国民健康保険」と「国民年金」からは脱退することになります。
- 「標準報酬月額」のマジック発動社会保険料は、「会社から貰っている給料の額(標準報酬月額)」で決まります。個人事業(A)でいくら数千万円稼いでいようが関係ありません。「法人(B)から貰っている給料が4万5000円」であれば、社会保険料はその金額をベースに計算されるのです。
結果として、社会保険料は**「もっとも安い等級(最低ランク)」**で固定されます。
これが、マイクロ法人による社会保険料削減の全貌です。
どれくらい安くなる?具体的な削減効果シミュレーション
言葉だけでは実感が湧かないと思いますので、数字でシミュレーションしてみましょう。
この差額を見れば、多少の手間をかけてでもやる価値があることがわかるはずです。
【モデルケース】
- 年齢: 40歳(介護保険あり)
- 家族: 妻(専業主婦)、子供1人
- 事業利益: 600万円(経費を引いた後の利益)
【Before】個人事業主のみの場合
今のまま国保を払い続けた場合です。
- 国民健康保険料:約75万円(所得割+家族3人分の均等割)
- 国民年金:約40万円(夫婦2人分 ※月額約1.6万円×12ヶ月×2人)
- 年間の支払総額:約115万円
利益600万円の中から、115万円が消えていきます。手取りは約485万円です。
【After】マイクロ法人設立(二刀流)の場合
法人を作り、役員報酬を月4.5万円に設定して社会保険に切り替えた場合です。
- 健康保険料(個人+法人負担分):約7万円/年
- 厚生年金保険料(個人+法人負担分):約19万円/年
- 年間の支払総額:約26万円
……いかがでしょうか?
個人の国保・国民年金は脱退して0円になり、法人で支払う社会保険料(約26万円)だけになります。
しかも、この社会保険料で**「妻と子供は扶養に入れる(追加負担0円)」ですし、「将来受け取る年金は厚生年金(2階建て)」**になります。
- Before:115万円
- After:26万円
- 差額:年間 約89万円の削減!
10年続ければ約900万円近い差になります。これだけのインパクトがあるため、多くの高所得フリーランスが導入しているのです。
もちろんデメリットもある!導入前に知るべき「コストと手間」
ここまでメリットばかり強調しましたが、法人を作る以上、コストやデメリットも確実に存在します。これらを天秤にかけて判断する必要があります。
1. 法人の維持費(赤字でも7万円)
法人は、利益が出ていなくても「存在しているだけ」で税金がかかります。
これを「法人住民税の均等割」と言い、年間約7万円です。
削減効果が数万円程度しかない場合は、この7万円で相殺されてしまうため、やる意味がありません。
2. 税理士報酬(ランニングコスト)
個人の確定申告は自分でやれても、法人の決算申告は非常に複雑で、素人がやるのは困難です。
基本的には税理士に依頼することになり、年間15万円〜30万円程度の費用がかかります。
(※最近は、マイクロ法人に特化した格安の税理士サービスや、自力で申告できるクラウドソフトも登場してはいます)
3. 社会保険の手続きが面倒
会社を作る登記手続き(約20〜25万円の初期費用)に加え、年金事務所への届出、毎月の給与計算、源泉所得税の納付、年末調整など、事務作業が発生します。
「とにかく事務作業はしたくない」という方にはストレスになるかもしれません。
4. 将来の年金額は増えない(iDeCo必須)
役員報酬を4.5万円に下げるということは、将来もらえる「老齢厚生年金」の額も最低ランクになるということです。
浮いた保険料を浪費するのではなく、iDeCo(iDeCoは引き続き加入可能です)やNISAに回して、自分で老後資金を作る必要があります。
まとめ:年収500〜600万円を超えたら「法人」という選択肢を
マイクロ法人は、決して「脱税」や「グレーな手法」ではありません。
個人事業と法人、それぞれの法的性格を理解し、適切に使い分ける「経営戦略」です。
導入を検討すべき目安ラインは以下の通りです。
- 課税所得(利益)が500万円〜600万円を超えている
- 扶養すべき家族(配偶者・子供)がいる
- 今後も安定して売上を維持できる見込みがある
これらに当てはまる方は、一度税理士に相談するか、シミュレーションをしてみることを強くおすすめします。
「知っている人だけが得をする」。残念ながらそれが今の日本の税・社会保険制度の現実です。
まずは「自分も対象かもしれない」と気づくことから、手取りを増やす第一歩を踏み出してみてください。
※免責事項
本記事は2025年時点の制度に基づき、一般的な仕組みを解説したものです。法人の設立や具体的な税務処理、社会保険の加入要件については、個別の事情により判断が異なる場合があります。実行の際は必ず税理士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。