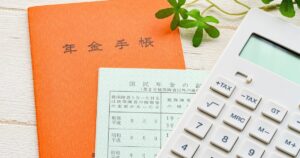会社を退職する際、手続き関連で最も頭を悩ませるのが「健康保険」です。
退職日が近づくと、人事担当者からこんな質問をされるはずです。
「退職後の健康保険、どうしますか? 任意継続しますか? それとも国保に切り替えますか?」
この質問をされたとき、あなたは自信を持って答えられるでしょうか。
「手続きが面倒だから、会社の保険をそのまま続けようかな……」
「国保の方がなんとなく安そうな気がする……」
もし、このような感覚だけで選んでしまおうとしているなら、少し待ってください。
この二択、実は選択を誤ると、年間で数万円、場合によっては十数万円もの「損」をしてしまう可能性があるのです。
会社員時代は給与天引きで自動的に処理されていた健康保険料ですが、退職後は「自分で選び、自分で払う」ものに変わります。そして、どちらを選ぶかによって、支払う金額が驚くほど変わるケースがあるのです。
この記事では、多くの退職者が直面する「任意継続 vs 国民健康保険」の問題について、FP(ファイナンシャルプランナー)の視点から徹底比較します。
それぞれの仕組みの違い、メリット・デメリット、そして「あなたがどちらを選ぶべきか」の判断基準(損益分岐点)をわかりやすく解説します。
退職後の生活費を守るために、賢い選択をしましょう。
まずは基本を知る!退職後の3つの選択肢
比較に入る前に、退職後の健康保険にはどのような選択肢があるのかを整理しておきましょう。実は選択肢は2つではなく、3つあります。
1. 家族の扶養に入る(最優先!)
これが最も負担の少ない、いわば「最強の選択肢」です。
配偶者や親、子供などが会社員として働いており、社会保険に加入している場合、その「被扶養者(扶養家族)」になれる可能性があります。
扶養に入ることができれば、**あなた自身の健康保険料は「0円」**です。
条件としては、「年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)かつ、被保険者の年収の2分の1未満」などの基準があります。
退職してしばらく収入がない場合や、失業給付を受けるまでの期間などは扶養に入れるケースも多いため、まずは「誰かの扶養に入れないか?」を最優先で検討してください。
2. 健康保険任意継続(任意継続)
これまで加入していた会社の健康保険に、退職後も個人として継続して加入する制度です。
「会社の保険証をそのまま(番号は変わりますが)使い続けられる」という安心感があります。最大で2年間加入できます。
3. 国民健康保険(国保)
お住まいの市区町村が運営する健康保険に加入し直す方法です。
自営業者やフリーランス、無職の方などが加入する保険です。
この記事では、多くの方が迷う**「2. 任意継続」と「3. 国民健康保険」のどちらが得か**について、深掘りして比較していきます。
「任意継続」vs「国民健康保険」決定的な4つの違い
金額を比較するためには、両者の「ルールの違い」を知る必要があります。特に「会社負担の有無」と「扶養の扱い」は、金額に直結する重要なポイントです。
1. 保険料の計算方法と「会社負担」の消失
ここが最大のショックポイントかもしれません。
- 任意継続の場合在職中の保険料は、会社とあなたで「折半(半分ずつ)」支払っていました。しかし、退職して任意継続をする場合、会社負担はなくなり、全額自己負担となります。単純計算で、**「在職中に給与明細で引かれていた額の約2倍」**になると考えてください。「会社を辞めたら収入がなくなるのに、保険料は倍になる」のです。
- 国民健康保険の場合前回の記事で解説した通り、あなたの「前年(1月〜12月)の所得」をもとに、自治体の計算式で算出されます。退職直後の年は、現役時代の高い所得をもとに計算されるため、高額になりがちです。
2. 「扶養家族」の保険料がかかるかどうか
ここが、どちらを選ぶかの勝敗を分ける最大の分岐点です。
- 任意継続の場合会社員の保険(社会保険)には、「扶養」という概念があります。専業主婦(夫)や子供を扶養に入れても、追加の保険料はかかりません(0円)。あなた1人分の保険料で、家族全員の保険証がもらえます。
- 国民健康保険の場合国保には「扶養」という概念がありません。妻も子供も、全員が「加入者」としてカウントされます。そのため、家族の人数分、「均等割(1人あたりにかかる料金)」が加算されます。家族が多ければ多いほど、国保の保険料は雪だるま式に増えていきます。
3. 保険料の「上限(キャップ)」の有無
高所得者だった方にとって重要なのがこのポイントです。
- 任意継続の場合保険料には「上限」が設定されています。多くの健保組合や協会けんぽでは、「標準報酬月額30万円(または28万円〜36万円程度)」が上限とされています。つまり、現役時代の給料が月50万円でも100万円でも、上限額以上の保険料は請求されません。
- 国民健康保険の場合国保にも上限(賦課限度額)はありますが、その設定額はかなり高めです(年間100万円近く)。高所得だった方は、任意継続の上限に守られた方が安く済むケースが多くなります。
4. 加入できる期間
- 任意継続: 最大2年間です。2年経つと強制的に脱退となり、国保へ切り替える必要があります(※就職した場合などを除く)。
- 国民健康保険: 期限はありません。再就職するか、75歳で後期高齢者医療制度に移るまで加入し続けられます。
【ケース別】どっちが得?判断するための「損益分岐点」
仕組みの違いがわかったところで、具体的なケースに当てはめて「どちらが安くなる可能性が高いか」を判定していきましょう。
ケースA:現役時代の給与が高く、扶養家族がいる場合
判定:【任意継続】が圧倒的に有利な可能性大
例えば、「月給40万円で、専業主婦の妻と子供2人を扶養している」ようなケースです。
- 任意継続: 保険料の上限(キャップ)が適用され、それ以上高くなりません。さらに、妻と子2人分の保険料はタダです。
- 国保: 所得が高いので所得割が高くなり、さらに妻と子2人分の均等割が上乗せされます。
このケースでは、任意継続の方が年間で10万円以上安くなることも珍しくありません。
ケースB:独身で、退職理由が「会社都合」の場合
判定:【国民健康保険】が有利な可能性大
リストラ、倒産、解雇、雇い止めなど、いわゆる「会社都合(非自発的失業)」で退職した場合は、国保に強力なメリットがあります。
**「軽減措置」**が適用されるからです。
これは、国保の計算の元となる前年の給与所得を**「30/100(30%)」とみなして計算してくれる**制度です。
所得が3分の1以下として計算されるため、保険料は激減します。この軽減措置は任意継続にはありません。
ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが該当すれば適用されますので、必ず確認しましょう。
ケースC:年収が低め〜平均的で、独身の場合
判定:【要シミュレーション(微妙なライン)】
「月給25万円前後で独身」といったケースは、最も判断が難しい「グレーゾーン」です。
任意継続(単純に2倍)と、国保(所得割+均等割)が拮抗します。
住んでいる自治体の国保料率によっても結果が変わるため、面倒でも両方の金額を試算する必要があります。
手続きの注意点!「20日ルール」と「空白期間」
どちらにするか決めたら、手続きの期限に注意してください。特に任意継続は非常にシビアです。
任意継続は「退職後20日以内」が絶対ルール
任意継続を希望する場合、退職日の翌日から20日以内に申請書を提出(必着の場合が多い)しなければなりません。
この期限を1日でも過ぎると、「理由を問わず一切受け付けない」という厳しい対応を取られることが一般的です。
「迷っていたら20日過ぎてしまった」という場合、強制的に国保しか選べなくなります。迷っているなら、退職前に書類を取り寄せておくのが無難です。
国民健康保険は「退職後14日以内」が目安
国保への切り替えは、退職日の翌日から14日以内に行うことになっています。
手続きには、会社から送られてくる「健康保険資格喪失証明書」が必要です。
14日を過ぎても加入自体はできますが、遅れた分の保険料も遡って請求される上、その間の医療費がいったん全額自己負担になるリスクがあるため、早めに済ませましょう。
まとめ:退職前に「試算」をしておくのが鉄則
退職後の健康保険料は、「知っているかどうか」だけで手元に残るお金が大きく変わります。
後悔しないための最強の手順は、以下の通りです。
- 【退職前】会社の担当者に聞く「任意継続をした場合、私の月々の保険料はいくらになりますか?」と確認します。
- 【退職前〜直後】役所に聞くお住まいの市区町村の国保年金課に電話をし、「前年の年収が〇〇円で単身(または家族〇人)なのですが、国保料の概算を教えてください」と聞きます。(自治体のWebサイトにある試算ツールも便利です)
- 【比較】安い方を選んで手続きする両方の金額が出揃ったら、安い方を選んで期間内に手続きをします。
退職前後は引き継ぎや引っ越しなどでバタバタしがちですが、この「ひと手間」を惜しまないことが、新生活の家計を守る第一歩です。
まずは、お手元の給与明細を見て、現在の健康保険料を確認することから始めてみてください。