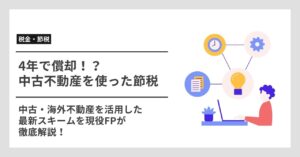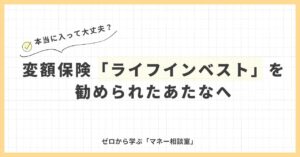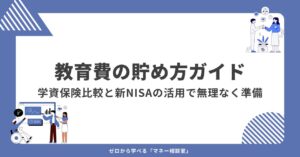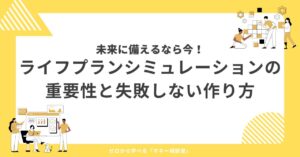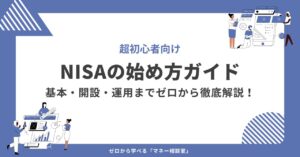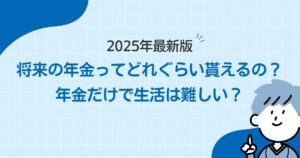「入院で医療費が十数万円もかかってしまった…」「手術代が高額で家計が不安」
そんな経験や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、医療費が一定額を超えた場合に、その超過分が後から戻ってくる「高額療養費制度」という仕組みがあるのをご存知ですか?
この制度を活用すれば、たとえば入院費が10万円かかっても、実際の自己負担は約8万円以下に抑えられることも。
しかも、家族の医療費を世帯で合算して申請できるケースもあるため、知っているかどうかで家計への影響は大きく変わります。
本記事では、そんな高額療養費制度について、
・制度のしくみと自己負担限度額
・家族で使える「世帯合算」のルール
・申請方法や注意点
・知らないと損する勘違いポイント
などを、一般家庭向けにやさしく解説していきます。
「もしもの医療費に備えておきたい」「医療費を少しでも節約したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
- 高額療養費制度は、公的医療保険に入っていれば誰でも使える「医療費の負担軽減制度」
- 世帯で医療費を合算できる「世帯合算」も有効
- 事前に「限度額適用認定証」を取得しておけば、窓口での支払いも抑えられる
- 知っているかどうかで家計への影響が大きく変わる

わがままボーヤ
マネー相談室長
本サイトを運営している現役FP
保険代理店で10年以上活動し2,000世帯以上とFP相談を行うも手数料ビジネスに嫌気がさし、FIREの実現を機に独立
商品を販売しない自由なFPとして、自分が本当に伝えたいことを「わがまま」に遠慮なく有益な情報をお届け!
はじめに|医療費が高くて困ったときに使える制度です
高額療養費ってどんな制度?
突然の入院や手術で、医療費が10万円、20万円と高額になることがあります。
そんなときに頼れるのが「高額療養費制度」です。
これは、公的医療保険に加入していれば誰でも利用できる仕組みで、1ヵ月の自己負担額がある一定の金額(=自己負担限度額)を超えた場合、その超過分を後から払い戻してくれる制度です。
たとえば、窓口で一度10万円を支払っても、後から3万円が戻ってくる――といったケースも珍しくありません
実は年間100万人以上が利用している制度です
この制度は一部の人だけのものではなく、一般家庭の誰もが使える生活支援制度です。
厚生労働省によれば、実際に毎年100万人以上がこの制度を活用しています。
しかし、意外と制度を知らず、申請もれで本来戻るはずだった医療費を受け取れないケースもあります。
「そんな制度があるなら、もっと早く知っておけばよかった…」と後悔する前に、ぜひ基本を押さえておきましょう。
自己負担はいくらまで?高額療養費の基本ルール
「自己負担限度額」ってなに?
高額療養費制度では、医療費が高額になっても、ある一定額(自己負担限度額)を超えた分は後から戻ってくる仕組みになっています。
この「一定額」というのが、「自己負担限度額」と呼ばれる金額で、年齢や所得に応じて細かく設定されています。
たとえば、70歳未満の方で年収約370万円〜770万円の「一般的な所得層」の場合、1ヵ月の自己負担限度額は約8万円(正確には80,100円+α)です。
つまり、それ以上支払った場合は「払いすぎ」となり、超過分が後日、健康保険から支給されます。
年齢と所得で決まる!限度額の早見表(70歳未満の場合)
| 所得区分 | 年収の目安 | 自己負担限度額(月額) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(上位) | 約1,160万円~ | 約25万~30万円 |
| 現役並み所得者(中位) | 約770~1,160万円 | 約16万 |
| 一般所得層 | 約370~770万円 | 約80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
| 住民税非課税世帯など | ~370万円未満 | 約35,400円~57,600円 |
医療費の「どこまで」が対象になるの?
高額療養費制度の対象になるのは、以下のような医療費です。
- 保険診療による入院・外来費用
- 手術費・検査費
- 薬代(院内・院外処方)
- 差額ベッド代(個室料金)
- 入院中の食事代(一定額の自己負担は発生)
- 保険適用外の自由診療(美容整形など)
「10万円払ったのに、戻ってきたのは1万円だけ?」というケースもありますが、それは対象外の費用が含まれている可能性があります。
領収書の内訳はしっかり確認しましょう。
家族みんなの医療費を合計できる!「世帯合算」とは?
世帯合算とは?|家族の医療費をひとまとめにできる制度
高額療養費制度では、同じ世帯で一定以上の医療費を支払った家族がいれば、金額を合算して自己負担限度額を超えるかを判定できる仕組みがあります。
これが「世帯合算」です。
たとえば、夫が入院で60,000円、妻が外来で45,000円の自己負担があった場合、個別には限度額を超えないかもしれませんが、合算して105,000円になれば、限度額を超えて高額療養費の対象になる可能性があります。
この制度により、「個別には対象にならなかったけど、合計したら戻ってくる!」というケースも多いのです。
70歳未満と70歳以上で仕組みが違う
実は、この「合算」にも年齢によるルールの違いがあります。
| 年齢 | 合算できる医療費の条件 |
|---|---|
| 70歳未満 | 1件あたり21,000円以上の自己負担のみが合算対象 |
| 70歳以上 | 原則としてすべての医療が合算対象(少額でもOK) |
そのため、70歳以上の方が複数人いる家庭では、比較的少額でも世帯合算で限度額を超えることがあり、戻ってくる金額が大きくなりやすいのです。
注意!合算できるのは「同じ保険」に加入している家族だけ
この制度で重要なのが、同じ医療保険に加入していることです。
たとえば、
✅ 夫と妻が両方とも「協会けんぽ」や「国民健康保険」に加入している → 合算OK
❌ 夫が「健康保険組合」、妻が「協会けんぽ」 → 保険が違うので合算できない
また、75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象)は、同制度に加入している人同士でしか合算できません。
世帯合算を活用するとどうなる?簡単なシミュレーション例
- 夫:自己負担 45,000円(外来)
- 妻:自己負担 60,000円(入院)
→ 合計:105,000円
→ 限度額超過分:105,000円-80,930円(仮)=24,070円が戻る!
手続きの方法とタイミングは?|もらい忘れに注意!
自動で支給される場合と、自分で申請が必要な場合
高額療養費は、ケースによって自動支給されることもあれば、申請が必要なこともあります。
| 支給方法 | 内容 |
|---|---|
| 自動支給(原則) | 医療機関から健康保険に請求が届いた後、数ヵ月後に自動で振込されることが多い |
| 申請が必要な場合 | 転院があった/複数の医療機関を受診した/世帯合算を希望するなど |
特に「世帯合算」や「限度額適用認定証を出していなかった場合」は、自動では払い戻されないこともあるので注意が必要です。
高額療養費の申請に必要なもの
申請が必要な場合は、次のような書類を用意して、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)に提出します。
- 高額療養費支給申請書(保険者のHPでダウンロード可)
- 健康保険証のコピー
- 医療費の領収書・明細書(支払額の確認用)
- 振込先の口座情報(世帯主名義が基本)
申請期限は原則2年以内ですが、「忘れていた」「気づかなかった」ケースも多いため、早めに提出することが大切です。
お金はいつ戻る?支給時期の目安
支給時期は健康保険によって異なりますが、申請から2~3ヵ月程度が一般的です。
ただし、以下のようなケースではさらに時間がかかることもあります。
- 医療機関からの請求処理が遅れている
- 世帯合算など、複雑な内容で申請している
- 書類の不備がある
また、会社員の方などで「給与天引きで医療費を支払っていた場合」は、健康保険組合を通じて会社経由で支給されることもありますので、総務担当に確認してみましょう。
よくある質問・勘違いポイント
「限度額適用認定証」って何?
高額療養費は、いったん医療費を全額(3割負担分)支払ったあとに戻ってくる仕組みですが、あらかじめ「限度額適用認定証」を提示しておけば、窓口での支払いそのものが少なくて済みます。
たとえば、本来10万円かかるところが、窓口での支払いが約8万円で済むようになります。
この認定証は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国保など)に申請すれば無料で発行されます。
入院が決まった時点で、できるだけ早めに申請しておくことをおすすめします。
差額ベッド代や食事代は戻らない?
高額療養費の対象になるのは、「保険診療」部分の医療費だけです。
そのため、次のような費用は対象外です。
| 対象外の費用 | 理由 |
|---|---|
| 差額ベッド代(個室料金など) | 自由診療扱い |
| 入院中の食事代 | 原則として自己負担(1食460円など) |
| 美容整形など保険外診療 | 完全自己負担 |
医療費の全額が戻るわけではないため、「戻ってくるはずが思ったより少なかった…」という誤解が生まれやすいので注意しましょう。
医療費控除と高額療養費は併用できる?
はい、併用可能です。ただし、少し注意が必要です。
医療費控除では、年間の医療費のうち、**「実際に自己負担した金額」**が対象になります。
つまり、高額療養費で戻ってきた分は差し引いて考える必要があります。
たとえば、
- 医療費合計:30万円
- 高額療養費で10万円戻ってきた
→ 医療費控除の対象は 20万円
税金の還付を受けるためには確定申告が必要です。年末調整だけでは申請できませんので注意しましょう。
高額療養費を活用して、家計の負担を減らそう!
こんなときに助かった!実際の活用事例
高額療養費制度は、いざというときに家計を大きく助けてくれます。以下は実際によくある活用例です。
例1:急な入院で医療費が15万円に!
→「限度額適用認定証」を提示していたため、支払いは約8万円に。
→ もし提示していなければ、いったん15万円を支払う必要があったところです。
例2:家族全員が風邪やけがで医療費がかさんだ月
→ 個別には対象にならなかったが、家族全員分を合算したら限度額を超え、高額療養費の支給対象に。
こうしたケースは決して珍しくなく、制度を知っているかどうかで大きな差になります。
高額な医療費が予想されるときの備え方
病気やけがは突然やってくるもの。ですが、以下のような備えをしておけば、いざというときにも慌てずに対応できます。
- 限度額適用認定証は常に準備しておく(とくに持病や入院予定がある方は必須)
- 領収書・明細は必ず保管(申請時に必要)
- 医療費の支出は家計簿やアプリで管理(申請や控除時の確認がラク)
さらに、民間の医療保険や共済に加入している方は、公的制度と合わせてどこまでカバーできるかも定期的にチェックしておくと安心です。
困ったときは専門家や保険者に相談を
高額療養費制度は、要件や計算方法がやや複雑なため、「自分は対象になるの?」「申請した方がいいの?」と迷う方も少なくありません。
そんなときは、以下のような相談窓口を活用しましょう。
- 加入している健康保険の窓口(協会けんぽ・市区町村の国保課など)
- ファイナンシャル・プランナー(FP)
- 社会保険労務士(医療費や社会保障の専門家)
「知っているだけで数万円得する制度」でもある高額療養費制度。
大切なのは、“いざというとき”の前に、制度の存在と使い方を知っておくことです。