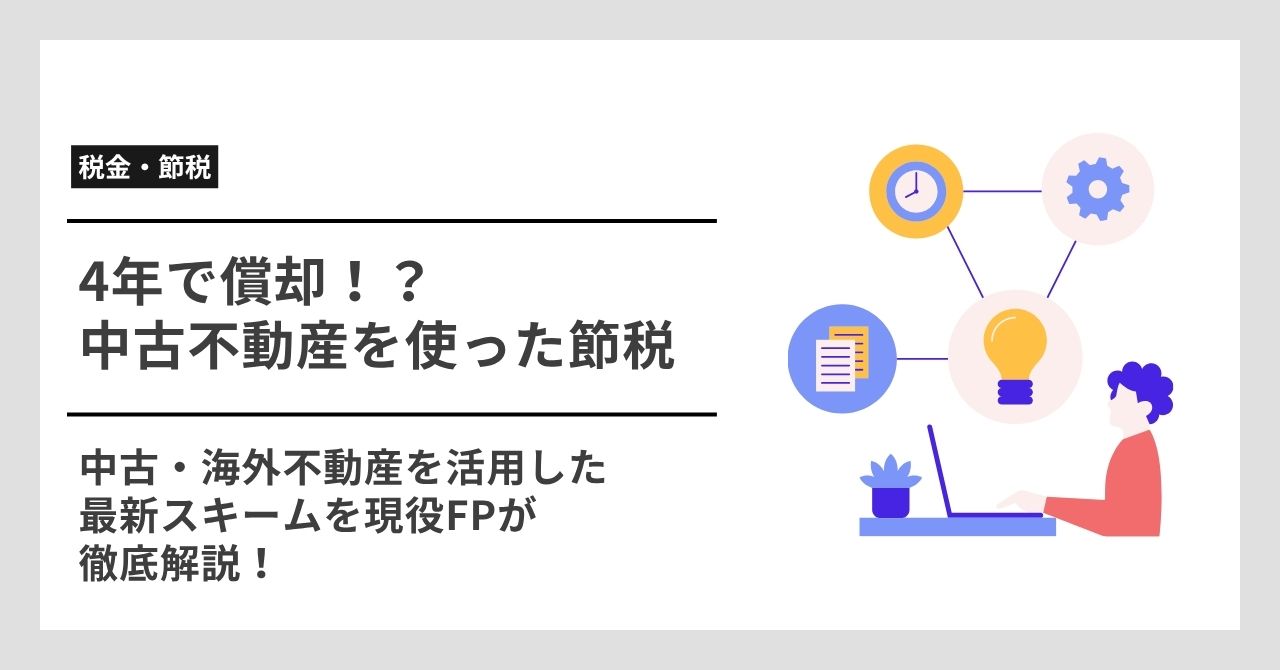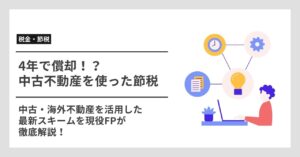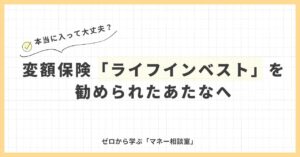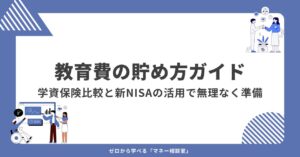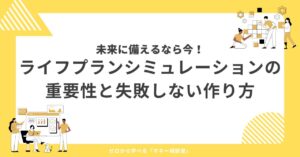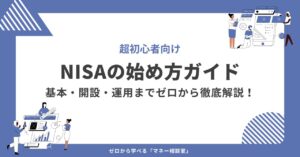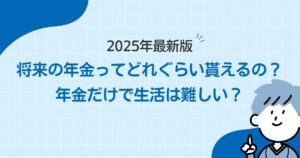相談者
相談者不動産で節税できるって本当ですか?うまく活用すれば資産も増やせると聞いたのですが・・・



不動産は減価償却費を多く計上できます。中でも、中古不動産は特殊な計算をするので、1年あたりの償却費が大きくできるメリットがあります。
法人税対策や資産形成において、中古不動産の減価償却や海外物件のメリットは、非常に大きなインパクトをもたらします。
この記事ではその仕組みや具体的なシミュレーション、さらには注意点まで詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 不動産を活用した節税が注目されている背景
近年、建設資材や人件費の高騰を背景に、新築物件の価格が上昇傾向にあります。
その影響で、割安な価格で取得できる「中古不動産市場」が活発化しています。
特に中小企業の経営者の間では、法人税の節税目的で中古不動産を活用するケースが増えています。
中古物件は、購入後すぐに減価償却を計上できるため、短期間で大きな経費処理が可能です。
これにより、当期の利益を圧縮し、法人税の支払いを抑えることができるのです。
2. 中古不動産を使った法人税対策の基本仕組み
不動産投資は「事業」として認められているため、関連する支出は経費として計上できます。
家賃収入や更新料が収入となる一方、経費には以下のようなものがあります。
・固定資産税、不動産取得税などの税金
・管理会社への管理料
・ローン金利
・減価償却費
・交通費や物件関連の出張費・飲食代(要件に合致する場合)
これらを差し引いた「不動産所得」が赤字となった場合、その損失を他の黒字事業の所得と相殺(損益通算)することが可能です。
法人全体の課税所得を圧縮できれば、結果として初年度の税負担を大きく軽減できるのです。
3. 節税のカギは「減価償却」にあり
法人税対策において最も重要なのが「減価償却」の考え方です。
新築物件の場合、法定耐用年数が長く、たとえば木造住宅なら22年かけてゆっくり償却していく必要があります。
一方で、中古物件の場合は「簡便法」と呼ばれる計算式を使うことで、より短期間での償却が可能になります。
法定耐用年数というのは、国であらかじめ決まっています。
| 建物の構造 | 用途 | 法定耐用年数 | 中古での簡便法による償却年数(築年数超過時) |
|---|---|---|---|
| 木造(戸建住宅) | 住宅用 | 22年 | 22年×0.2=4年 |
| 軽量鉄骨造(厚さ3mm以下) | 住宅用 | 19年 | 19年×0.2=3年 |
| 鉄骨造(厚さ3mm超~4mm以下) | 事業用 | 27年 | 27年×0.2=5年 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | マンション・ビル | 47年 | 47年×0.2=9年 |
上記の通り、木造住宅なら22年です。
つまり、築22年以上経過した中古の木造住宅であれば、
22年 × 0.2 = 4.4年 → 4年(切り捨て)
となり、たった4年で建物価格の全額を経費にできるのです。
同じ4,000万円の物件でも、新築RC造(鉄筋コンクリート)の場合は1年の償却額が85万円程度に留まる一方、中古木造なら2,000万円以上を1年で経費化できるケースもあります。
つまり、中古不動産の最大の魅力は「短期間で大きな減価償却を計上できること」なのです。
4. 海外不動産の節税メリットとは?
節税において注目されているのは日本国内の中古物件だけではありません。
海外不動産、特にアメリカの物件にも大きなメリットがあります。
① 建物割合が高い
② 「4年」で償却が可能
③ 資産価値が落ちにくい
- ① 建物割合が高い
-
アメリカでは不動産価格のうち建物の占める割合が70〜80%と高く、日本の20〜40%に比べて圧倒的です。
減価償却できるのは建物部分のみなので、建物割合が高ければそれだけ多くの経費が計上できます。
- ② 「4年」で償却が可能
-
日本法人がアメリカ不動産を所有する場合でも、日本の税制に従って減価償却が行われます。
築年数の経過した木造物件であれば、日本国内と同様、4年で償却が可能です。
- ③ 資産価値が落ちにくい
-
アメリカでは「中古住宅をリノベーションして再販する」文化が根づいており、築100年超の住宅も現役です。
物件供給が限られていることもあり、むしろ価値が上昇していくケースも珍しくありません。
つまり、節税しながら、将来的なキャピタルゲイン(売却益)も見込めるのがアメリカ不動産の強みといえるでしょう。
5. 海外不動産の節税効果をシミュレーション
ここでは、アメリカの中古不動産を購入した場合の減価償却効果を具体的な数値で見ていきましょう。
・物件価格:37万ドル(約5,180万円)
・築年数:23年(木造)
・建物割合:86%(約32万ドル=約4,480万円)
・償却期間:4年間(簡便法により)
※為替レートは1米ドル=140円で固定
この場合、減価償却対象額は約32万ドル。これを4年で均等償却するため、
年間約8万ドル(約1,120万円)を経費として計上することができます。
つまり、初年度から毎年1,000万円超の減価償却を計上し、課税所得を大幅に減らせるということです。
実質利回りは2〜3%程度と控えめですが、「節税+資産形成」の視点では非常に大きなインパクトがあります。
6. 海外不動産のリスクと注意点
魅力的な節税効果がある一方で、海外不動産には注意すべきリスクも存在します。
代表的なリスクは以下の3つです。
① 為替リスク
② 管理リスク
③ カントリーリスク・制度リスク
- ① 為替リスク
-
円安が進むと売却時に円ベースでの損失が出る可能性があります。
逆に円高になると、円建ての取得コストが上がるため、購入タイミングが重要になります。
- ② 管理リスク
-
現地の物件を自分の目で確認したり、直接やり取りしたりするのは難しいため、信頼できる現地の管理会社選びが最重要課題となります。
管理がずさんな業者に委託すると、空室やトラブルが増え、収益に大きく影響します。
- ③ カントリーリスク・制度リスク
-
不動産に関する法制度や税制が日本と異なるため、事前に制度を十分に理解しておく必要があります。
場合によっては、現地の法律変更により税制優遇が受けられなくなる可能性もあります。
7. 【まとめ】節税と資産運用は「仕組み」と「計画」が鍵
今回ご紹介したように、中古不動産や海外不動産を活用することで、法人税を大幅に圧縮しつつ資産形成を図ることが可能です。
しかし、これらの手法は正しい知識と戦略、そして信頼できるパートナーがあってこそ、真の効果を発揮します。
特に、以下のような方には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
・節税だけでなく、キャッシュフローや資産全体の最適化を考えたい
・海外不動産に初めてチャレンジするので、現地管理や法制度が不安
・減価償却だけでなく「出口戦略」まで含めて相談したい
不動産を活用した節税対策は、単なる経費処理ではなく、経営と資産戦略を一体化する力強いツールです。
中古不動産の減価償却、海外物件の建物割合、そして繰延べ税のコントロール。
これらをうまく組み合わせることで、「税負担を減らしつつ、会社の資産も増やす」という理想的な形が実現します。
節税はゴールではありません。あくまで、企業が健全に成長し続けるための手段です。
ぜひこの機会に、ご自身の事業に合った不動産活用の可能性を考えてみてはいかがでしょうか?