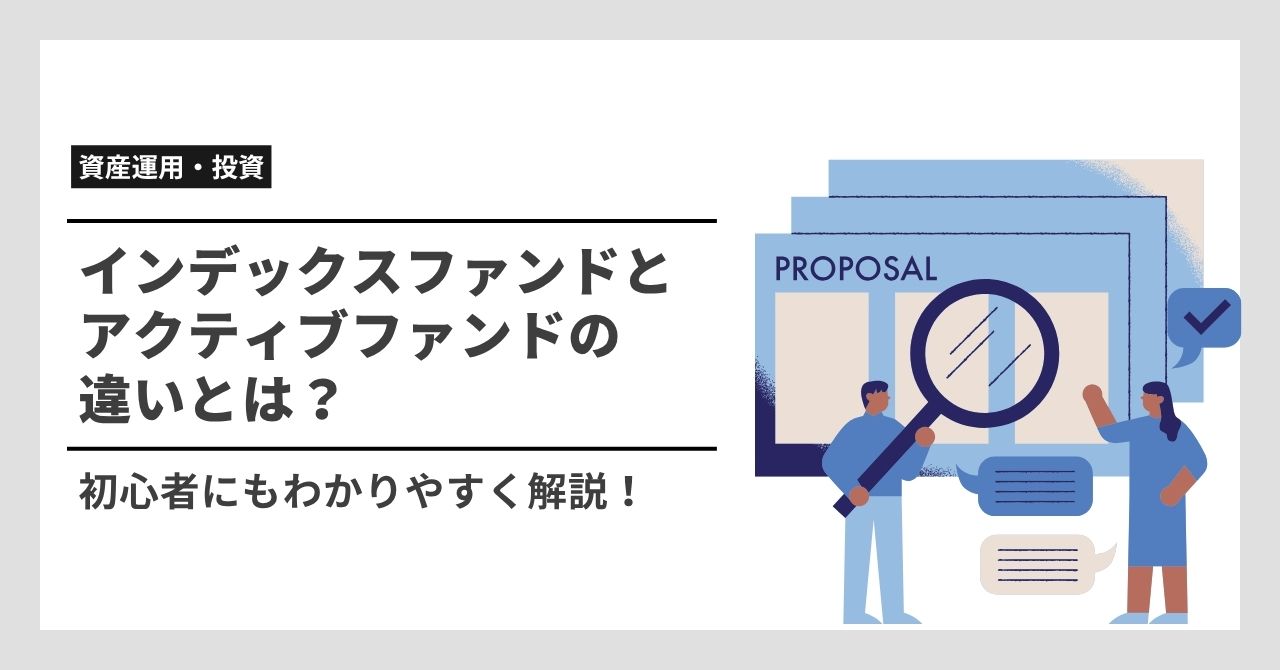「投資信託を始めたいのですが、2種類のタイプがあると聞きました。それぞれの違いを教えてください。」
「インデックスファンドとアクティブファンドですね。この違いは投資信託を始める上で基本となる部分ですので、しっかり確認していきましょう」
数ある投資信託は全てこの2つに大別されます。
とくに、つみたてNISAやiDeCoなどをきっかけに投資を始めた方にとって、「ファンドの選び方」というのは最初に考える非常に大きなテーマです。
この記事では、ファンド選びにおいてよく話題になる「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の違いについて、わかりやすく解説していきます。
それぞれの特徴やコスト、リターンの違いを比較しながら、あなたに合った選び方もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!
1.投資信託は2種類に大別されます
投資信託には大きく分けて「インデックスファンド」と「アクティブファンド」の2種類があります。
これらは、運用の方針や目的が大きく異なるため、まずはその違いをしっかり理解しておくことが大切です。
インデックスファンドとは
インデックスファンドは、特定の指数(インデックス)に連動する運用を目指す投資信託です。
たとえば、日本株全体を表す「日経平均株価」や「TOPIX」、米国株の代表である「S&P500」などの動きに連動するように、機械的に銘柄を組み入れて運用されます。
つまり、インデックスファンドは「市場全体の平均的な成績を目指す」運用スタイルといえます。
- 銘柄選びは指数に従って自動的に行われる
- 運用コストが安い
- 手堅く市場平均のリターンを狙う
アクティブファンドとは
アクティブファンドは、市場平均(インデックス)を上回るリターンを目指す運用スタイルです。
ファンドマネージャーが市場や企業の分析を行い、有望と判断した銘柄を選んで積極的に投資します。
つまり、「この銘柄は将来伸びる」といった判断に基づいて、プロの手腕でパフォーマンス向上を狙うのがアクティブファンドです。
- 運用担当者の判断によって銘柄を選ぶ
- 成績が良ければ高いリターンが期待できる
- ただし運用コストは高め
2.運用コスト(手数料)の違い
インデックスファンドとアクティブファンドの大きな違いの一つが、「運用コスト(手数料)」です。
長期投資においては、コストの差が最終的なリターンに大きな影響を与えるため、しっかり理解しておきましょう。
3つの運用コスト
運用コストは大きく3つ存在します。
3つの運用コスト
・購入時手数料(販売手数料)
・信託報酬
・信託財産留保額
3つの手数料の中で1番見るべき部分は『信託報酬』です。
投資信託の運用や管理にかかる費用を表しています。
これは保有している間ずっとかかる「年率制」の手数料で、ファンドの資産から自動的に引かれます。
信託報酬の差
インデックスファンド
年0.1~0.3%前後 と低コストです。
→指数に連動させるだけなので、人件費や分析コストが抑えられます。
アクティブファンド
年0.5~2.0%程度 が多く、インデックスファンドよりも高めです。
→プロの分析やリサーチにコストがかかるため、その分信託報酬も高くなります。
購入時手数料(販売手数料)は、現在ではノーロード(無料)のファンドが増えてきており、特につみたてNISA対象ファンドは購入手数料が無料です。
一部のファンドでは、解約時に「信託財産留保額」がかかることもあります(数%程度)。
ただし、これもインデックスファンドではほとんど見られません。
長期投資ではコストの差がリターンに影響
たとえば、年間1.5%の信託報酬差が20年間続くと、投資元本の数十万円以上が目減りすることもあります。
図
同じ成績でも、手数料が低い方が「実際の手取りリターン」が大きくなるため、コストは見逃せないポイントです。
3.パフォーマンスやリスクの違い
インデックスファンドとアクティブファンドでは、運用成果やリスクの取り方にも明確な違いがあります。
「どちらが儲かるのか?」という視点で気になる方も多いですが、ここではそれぞれのパフォーマンス傾向とリスクの違いを解説します。
平均的なリターンの傾向
インデックスファンド
市場全体に広く分散投資するため、安定したリターンが期待できます。
例えば、米国の「S&P500連動型インデックスファンド」は過去20年で年平均7〜10%程度のリターンを出している実績もあります。
アクティブファンド
市場平均を上回るリターンを目指しているため、一部のファンドは高い成績を出すこともあります。
しかし、実際には大多数のアクティブファンドが長期的にインデックスを上回れないというデータもあります。
(例:米国の調査では、10年で市場平均に勝てたアクティブファンドは2割以下)
リスク(値動きのブレ)の違い
インデックスファンド
分散が効いている分、値動きが比較的穏やかです。
急騰・急落が少ないため、長期保有に向いています。
アクティブファンド
銘柄を絞って投資する傾向があるため、値動きが激しくなることがあります。
特定の業種やテーマに集中するファンドは、大きな利益と損失の両方の可能性を持っています。
成績の良いアクティブファンドを選ぶのは難しい
「じゃあ成績の良いアクティブファンドを選べばいいじゃないか」と思うかもしれません。
しかし、過去に好成績だったファンドが今後も好調とは限らないのが投資の難しさです。
そのため、投資初心者にとっては「成績の見極めが難しい」点もアクティブファンドのデメリットとなることがあります。
4.初心者に向いているのはどっち?目的別の選び方
ここまでインデックスファンドとアクティブファンドの違いを解説してきましたが、「で、結局どっちがいいの?」というのが一番気になるポイントですよね。
結論からいえば、どちらが正解というわけではなく、「投資の目的」や「投資スタイル」によって選ぶべきファンドは変わってきます。
以下に、ケース別のおすすめをまとめました。
初心者・投資に不安がある人
→ インデックスファンドがおすすめ
- 手数料が安く、長期的に市場平均のリターンが狙える
- 銘柄選びの必要がなく、ほったらかし投資ができる
- つみたてNISAやiDeCoでも主力商品として使われている
特に「S&P500連動型」や「全世界株式型(オルカンなど)」のインデックスファンドは、リスク分散もしやすく、初心者でも安心して長期投資に取り組めます。
市場平均以上の成果を目指したい・テーマ投資に興味がある人
→ アクティブファンドを検討してもOK
- プロの運用に期待したい
- 特定の業種や企業に強い関心がある
- リスクを取ってでもリターンを追求したい
ただし、アクティブファンドを選ぶ際は「手数料が高すぎないか」「運用実績が安定しているか」など、慎重な見極めが必要です。
インデックスとアクティブ、併用もアリ
たとえば、「資産の8割はインデックスでコツコツ積立て、2割はアクティブファンドでチャレンジ枠にする」といったハイブリッド型の運用も有効です。
自分の投資経験や資産状況に応じて、柔軟に使い分けていくのもひとつの選択肢です。
5.まとめ
インデックスファンドとアクティブファンドには、それぞれ異なる特徴やメリット・デメリットがあります。
| インデックスファンド | アクティブファンド | |
|---|---|---|
| 運用方針 | 指数に連動 | 市場平均を上回ることを目指す |
| コスト | 低い(年0.1~0.3%) | 高い(年0.5~2.0%) |
| リターン | 市場平均に準ずる | 優秀なファンドは高リターンも可能 |
| リスク | 分散性が高く安定 | 集中投資により変動が大きいことも |
| 初心者向きか | ◎ | △(選定力が必要) |
初心者はインデックスファンドがおすすめ
初心者の方や長期投資を考えている方には、まずはインデックスファンドを中心に据えるのが基本です。
NISAの買付ランキングでも常にトップになるほど超人気であり、どんな投資家でも一部はインデックス投資をしているのがほとんどです。
まずはベースとしてインデックス投資を行い、その上で投資に慣れてきたらアクティブファンドにチャレンジしてみるのも良いでしょう。
大切なのは、「どちらが正解か」ではなく、自分の投資目的と相性のよいスタイルを見つけることです。
焦らず、無理なく、コツコツと自分に合ったファンドで、着実に資産形成を進めていきましょう。